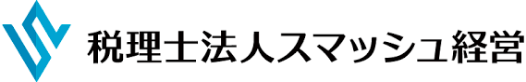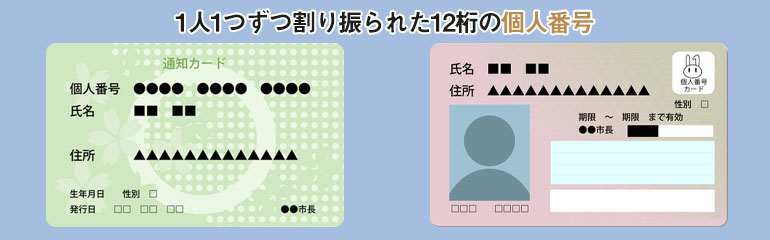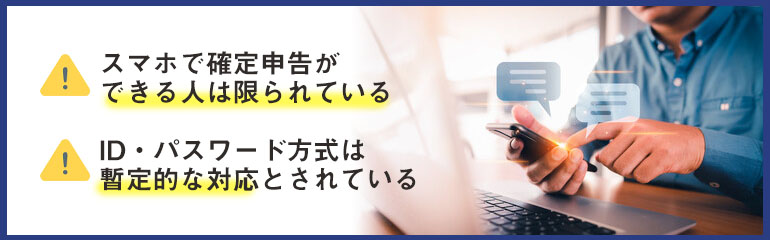税務情報
2022.12.28
スマホでの確定申告はマイナンバーカードなしでできる?やり方を解説
スマホで確定申告を行う際に、マイナンバーカードが必要かどうか分からない方も多いのではないでしょうか。
マイナンバーカードがなくても、確定申告はスマホで手続きできますが、将来的にマイナンバーカードが必須となる可能性もあるため、注意が必要です。
そこで本記事では、混同しがちなマイナンバーとマイナンバーカードの違い、スマホで確定申告を行う際の注意点などを解説します。
スマホ1つで簡単に確定申告をしたい方、マイナンバーカードがなくても確定申告ができるのか知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
1.確定申告に必要なマイナンバーとは?
マイナンバーとは、住民票を有するすべての人に、1人1つずつ割り振られた12桁の個人番号のことです。行政の効率化と国民の利便性向上を図り、公平・公正な社会を実現するための社会基盤という位置付けで導入されました。
出典:地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト「マイナンバー(個人番号)とは – マイナンバーカード総合サイト」
マイナンバーとマイナンバーカードを混同して考えられることもありますが、この2つには違いがあります。マイナンバーは「個人個人に割り振られた番号そのもの」を指す言葉で、マイナンバーカードは「マイナンバーが記載されたカード」のことです。
マイナンバーカードには、マイナンバーのほかに、氏名や住所、生年月日、性別、本人の顔写真が表示されます。マイナンバーカードは本人確認書類として使用できるほか、自治体サービスやe-Taxによる電子申請などのサービスにも利用できます。
出典:地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト「マイナンバーカードについて – マイナンバーカード総合サイト」
1-1.確定申告にはマイナンバーが必要
確定申告の際には、マイナンバーの記載が必須です。確定申告書の1ページ目にマイナンバーを記載する欄があり、給与を支払う必要がある配偶者や扶養親族などがいるケースでは、一人ひとりの番号を記載する必要があります。
また、マイナンバーは、確定申告を行う際に毎回記載しなければなりません。マイナンバーカードの取得は必須ではありませんが、取得しておけばマイナンバーの本人確認が簡単になるため、入手しておくのがおすすめです。マイナンバーカードを持っておけば、確定申告書提出の際に番号確認と身元確認がカード1枚の提示で済むというメリットもあります。
1-2.マイナンバーの確認方法は?
マイナンバーカードを取得しておらず、マイナンバーの確認方法が分からない方もいるのではないでしょうか。確定申告にはマイナンバーが必須なため、マイナンバーが分からない場合はあらかじめ確認しておく必要があります。
マイナンバーは、「マイナンバー(個人番号)記載の住民票の写し」または「通知カード」から確認できます。通知カードとは、マイナンバーを知らせるために平成27年10月から12月に送付された緑色のカードです。通知カードは、マイナンバーカードの交付を受ける際に返納する必要があります。
通知カードの発行は、令和2年5月に廃止されました。そのため、通知カードとマイナンバーカードが両方ない場合は「マイナンバー記載の住民票の写し」もしくはマイナンバーカードを入手することでマイナンバーを確認できます。
なお、「マイナンバー記載の住民票の写し」は即日受け取り可能ですが、マイナンバーカードは申請から受け取りまでに1か月ほどかかるため注意しましょう。
出典:地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト「通知カードについて – マイナンバーカード総合サイト」
2.マイナンバーカードがなくてもスマホで確定申告ができる?
スマホで確定申告をするには、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用します。
e-Taxとは、インターネットを通じて所得税や法人税、消費税、贈与税、印紙税、酒税などの申告を含む各種手続きができるものです。e-Taxを利用すると、スマホやPCから確定申告・税金の納付などの手続きを行うことができます。
出典:e-Tax国税電子申告・納税システム「e-Taxについて知る | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)」
確定申告でe-Taxを利用するための方法として、「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」があります。
スマホで確定申告を行う際にマイナンバーカードが必要となるのは、マイナンバーカード方式の場合です。マイナンバーカード方式では、マイナンバーカードの読取に対応した機種のスマホでマイナンバーカードを読み取ることによってe-Taxの利用が可能になります。
ID・パスワード方式でe-Taxを利用する場合は、マイナンバーカードは使いません。税務署においてe-TaxからID・パスワード方式の届出を作成・送信することにより、e-Taxで確定申告などの手続きが可能になります。
出典:国税庁「e-Taxの事前準備のご案内:令和3年分 確定申告特集」
出典:e-Tax国税電子申告・納税システム「ID・パスワード方式について| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)」
2-1.ID・パスワード方式で確定申告を行うには?
e-TaxをID・パスワード方式で利用し、確定申告を行うためには、税務署においてe-Taxでの手続きが必要です。自宅からWEBにアクセスして手続きをする場合はマイナンバーカードが必要となるため、マイナンバーカードを持っていない方は税務署で手続きをすることになります。
税務署でのID・パスワード方式の手続きのステップは以下の通りです。
| 1 | 本人確認をしてもらう |
|---|---|
| 税務署に行き、職員との対面によって本人確認をしてもらいます。この際、運転免許証や健康保険証などの本人確認書類が必要になるため、必ず用意しましょう。 | |
| 2 | 届出の作成・送信 |
|---|---|
| 税務署内で、ID・パスワード方式の届出を作成・送信すると、利用者識別番号を取得できます。この利用者識別番号があれば、e-Taxを利用できるようになります。 | |
なお、WEBの場合は、国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」からマイナンバーカードを使って届出を作成・送信することで手続きが可能です。
3.スマホで確定申告をする際に必要なもの

ここからは、スマホで確定申告を行う場合に、あらかじめ用意しておく必要があるものを紹介します。
なお、スマホが必要となりますが、すべての機種が対応している訳ではないため、注意が必要です。
なお、対応機種一覧はマイナポータルの公式サイトに掲載されています。お使いの機種が対応しているかどうか、事前に確認しておくと良いでしょう。
マイナンバー
マイナンバーカード方式で確定申告を行う場合は、手元にマイナンバーカードを用意しておきましょう。
なお、マイナンバーカードを発行していない方は、前述の通り「ID・パスワード方式」で確定申告を行うことが可能です。
ただし、ID・パスワード方式を選択した場合でも、申請時にマイナンバーを記入する必要があります。
もしもマイナンバーカードがない場合は、通知カードもしくはマイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しを用意し、必要に応じていつでも入力できるように準備しておきましょう。
源泉徴収票
会社員や給与収入がある方は、勤め先で発行された源泉徴収票が必要です。
源泉徴収票とは、年間の給与収入や納付した所得税額などが記載された書類のことです。
万が一紛失した場合は、職場に連絡すると再発行してもらえます。
なお、源泉徴収票に添付義務はありませんが、金額を確認する際に使用するため、事前に用意しておきましょう。
領収書・控除を受けるための証明書
スマホで確定申告する際に、医療費控除などの控除枠を利用する人も多いでしょう。
医療費控除以外にも、生命保険料控除や地震保険料控除などを受ける場合は、領収書や控除証明書の用意が必要です。
なお、領収書は確定申告書に添付するのではなく、スマホで送信しますが、5年間は保管しなければいけないため、捨てずに保管しておきましょう。
また、マイナポータルと連携することにより、自動的に控除証明書の内容が反映されるため、入力の手間が省けて便利です。
スマホで確定申告を行う操作手順

ここからは、スマホで確定申告を行う操作手順について、解説していきます。
スマホから確定申告書等作成コーナーにアクセスし、内容を送信するまでの一連の手順を紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
確定申告書等作成コーナーへアクセスする
まずは、スマホで「確定申告書等作成コーナー」と検索し、国税庁のサイトにアクセスします。
続いて、画面中央あたりに表示されている「作成開始」をクリックして、さっそく操作を進めていきましょう。
作成する申告書を選択する
「作成開始」を押すと、作成する申告書を選択する画面がスマホに表示されるため、目的に応じて選んでください。
選択する申告書は、収入などの状況によって異なり、具体的には以下の3つがあります。
- 所得税:所得税の申告書を作成する方
- 決算書・収支内訳書(+所得税):事業所得や雑所得などがあり、青色申告決算書や収支内訳書も一緒に作成したい方
- 消費税:事業や不動産貸付をしており、課税事業者の方
申告書を選択したら年度が表示されるため、該当するものを選択しましょう。
提出方法にチェックを付ける
作成する申告書・年度をクリックして画面を下に進めると、提出方法が問われます。
選択できる提出方法は、以下の3つです。
- e-Tax(マイナンバーカード方式)
- e-Tax(ID・パスワード方式)
- 書面
e-Taxから申請する場合は、マイナンバーカードを利用するか「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたID・パスワードを入力するかで異なります。
マイナンバーカード方式を選択すると、マイナポータルと連携するか確認する画面が表示されます。
マイナポータルと連携すると、申告に必要な証明書などのデータを一括で取得して自動入力されるため便利です。
なお書面とは、確定申告書等作成コーナーで作成した申告書を書面に出力して、提出する方法です。
質問内容に答える
提出方法をクリックしたら、申告内容に関する質問に回答していきます。
申告する収入の項目(給与や公的年金など)を問われるため、該当するものを選びましょう。
マイナポータルアプリをダウンロード
e-Tax(マイナンバーカード方式)を利用するためには、お使いのスマホへマイナポータルのアプリが必要です。
ダウンロードしていない場合は画面に表示されているアイコンをクリックして、アプリを入手しましょう。
続いて、次のページに進む前に利用規約への同意が求められるため、内容を確認した後に「同意して次へ」をタップします。
なお、ID・パスワード方式を選択した場合は、アプリのインストールは不要です。
マイナンバーカード認証をする
マイナポータルアプリをインストールしたらログインをして、マイナンバーカードを読み取ります。
マイナンバーカードの読み取りが完了後に登録情報が表示されるため、間違いがないか確認して「次へ」を選択してください。
マイナポータル連携をする
先ほど「マイナポータルとの連携」を選択した場合は、マイナポータル連携をするための画面が表示されます。
申請者本人の情報を取得する場合は「取得する」を選択し、利用規約や証明書等の確認をして「次へ」をクリックします。
マイナポータルとの連携によって取得した情報が表示されるため、金額や内容を確認しましょう。
必要情報を入力して送信する
続いて1年間の給与や所得控除、住宅ローンなどの確定申告に必要な情報に回答していきます。
入力が完了したら計算結果と納付方法についての案内が表示されるため、次の画面で氏名や住所、生年月日などの必要事項に回答して、マイナンバーを入力します。
もしも作業を中断させたい場合は、作成画面の下部にある「ここまでの入力内容を保存」をタップして「入力データをダウンロードする」を選択すると、一時保存が可能です
申告内容の確認
申告書を送信する前に帳票イメージを確認できるため、誤りがないかチェックしたら「次へ」をタップします。
送信準備として特記事項の有無を問われるため、ない場合は「次へ」をクリックしてください。
次に申告書を送信するための画面が表示されるため「送信する」を押して、確認画面が表示されたら「送信を実行する」を選択してください。
ID・パスワード方式を利用している場合は、申告書を送信する前に暗証番号を入力してから「送信する」をクリックしましょう。
送信が完了すると「送信完了」とともに、青いチェックマークが表示されるため「閉じる」を押します。
続いて、送信結果の確認として氏名や受付番号、内容などが表示されるので「次へ」ボタンをタップして、送信票等の印刷画面に進みます。
送信後の申告書の控えは印刷やデータでの保存も可能なため、保管しておくと良いでしょう。
スマホから確定申告書の作成・送信は以上のため、手順を確認しながら実行しましょう。
5.確定申告をスマホで行う際の注意点
スマホで確定申告ができれば、税務署に行く手間や時間を省けるため非常に便利です。確定申告は毎年行う必要がある方もいますし、確定申告にかかるすべての手続きをスマホ1つで完結させたい方も多いのではないでしょうか。
しかし、マイナンバーカードなしでもスマホで確定申告は行えるものの、以下の点に注意する必要があります。
3-1.スマホで確定申告ができる人は限られている
スマホで確定申告を行う場合、申告できる所得が限られています。スマホでの確定申告の対象となる所得は、以下の通りです。
- 給与所得
- 雑所得
- 一時所得
- 特定口座年間取引報告書(上場株式などの譲渡所得等、配当所得等)
- 上場株式等の譲渡損失額(前年度に繰り越した分が対象)
例えば、給与所得のある会社員や、年金収入のある方、副業などの雑所得がある方は、スマホでの確定申告が可能となります。しかし、事業所得や不動産所得がある方はスマホからの確定申告が行えないため注意が必要です。
なお、所得控除については、すべての所得控除がスマホによる確定申告の対象となっています。会社員などの給与所得者で、医療費控除やふるさと納税などの寄附金控除を受ける場合は、スマホでの確定申告が便利です。
3-2.ID・パスワード方式は暫定的な対応とされている
ID・パスワード方式は、マイナンバーカードが一般に普及するまでの暫定的な対応とされています。そのため、早めにマイナンバーカードを取得しておくと安心です。
出典:国税庁「ID・パスワード方式について| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)」
ここからは、マイナンバーカードの取得方法について説明します。
| 1 | 申請をする |
|---|---|
| マイナンバーカードの申請を行います。申請方法は、個人番号通知書や通知カードに同封されている交付申請書などを利用した郵送申請、オンラインでの申請、証明写真機による申請などです。なお、証明写真機は申請できないものもあるため注意してください。 | |
| 2 | 交付通知書が届く |
|---|---|
| 審査が完了すると、1か月ほどでマイナンバーカードが発行され、市区町村に送付されます。その後、マイナンバーカードを受け取った市区町村によって、申請者に交付通知書が送付されます。 | |
| 3 | マイナンバーカードを受け取る |
|---|---|
| 交付通知書が手元に届いたら、市区町村の窓口に行ってマイナンバーカードを受け取りましょう。交付通知書に記載された期日までに、本人が窓口に受け取りに行ってください。 | |
出典:地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト「申請・受取方法/申請状況確認 – マイナンバーカード総合サイト」
6.e-Taxと確定申告書等作成コーナーの違いは?
e-Tax・確定申告書等作成コーナーは、ともにインターネットを利用して確定申告書が作成できるサービスですが、その目的が異なります。
e-Taxは確定申告書を送信するシステムであり、確定申告書等作成コーナーは申告書を作成するためのシステムです。
確定申告書等作成コーナーで申告書を作成し、そのデータをe-Taxを使って送信することで、オンライン申告が完了します。
このように、それぞれで役割が分かれているため、事前に違いを整理しておきましょう。
まとめ
スマホでの確定申告は、マイナンバーカードがなくても行えます。しかし、スマホで確定申告できる人は限られているため注意が必要です。マイナンバーカードを利用しないID・パスワード方式に関しても暫定的な対応のため、早めにマイナンバーカードを取得しておくことをおすすめします。
マイナンバーカードは1枚で本人確認書類として利用できたり、役所に行かなくても公的な証明書をコンビニで発行できたりとメリットも複数あります。確定申告時にもマイナンバーの確認が簡単にできるので、マイナンバーカードを持っていない方や通知カードの情報が古くなっている方はぜひ取得を検討してみてください。
監修者情報

税理士法人スマッシュ経営
中垣 泉(なかがき いずみ)
資格:税理士
経歴
- 1951年
- 愛知県豊田市生まれ
- 1974年
- 名古屋国税局採用
- 1992年
- 法人税担当統括官
- 2012年
- 名古屋国税局退職
税理士登録
税理士法人スマッシュ経営 岡崎オフィス入社
社員税理士となる - 2019年
- 税理士法人スマッシュ経営
岡崎オフィス所長就任 - 2021年
- 岡崎オフィス所長兼代表社員へ就任