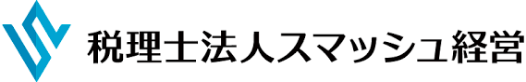税務情報
2025.07.10
法人税の中間申告の時期は?計算方法や注意点も紹介
本記事では法人税の中間申告が必要となるケースや申告時期、計算方法について詳しく解説していきます。
納付を忘れた場合のリスクも紹介しているので、法人税の中間申告を正しく理解したい方はぜひ参考にしてください。
目次
法人税の中間申告とは
法人税は年2回の申告が必要
中間申告は、仮決算に基づく方法と前事業年度の実績を基準とする方法(予定申告)2つの方法があります。
中間申告の対象
● 株式会社や合同会社などの普通法人で事業年度が6か月を超える法人
● 前事業年度の法人税額を前事業年度の月数で除し、これに中間期間の月数を乗じて計算した金額が10万円を超える法人
設立1年目の法人の場合は中間納付の対象外となりますが、合併した法人は1年目であっても中間納付が必要になることがあるため気を付けてください。
なお、公益法人や協同組合等、人格のない社団・財団は中間申告の対象外になります。
2通りの申告方法
どちらの方法にするかは法人が任意に選択でき、事前の申請は不要です。
また、今期は仮決算で申告して、翌期は予定納税で申告するといったように、毎期違う方法で申告することも可能です。
なお、仮決算に基づく中間申告は決算書等の作成が必要であり時間もかかるため、仮決算の方法にする決定は早期に行い、準備をしておくようにしましょう。
前年度実績を基準とする中間申告(予定申告)による方法
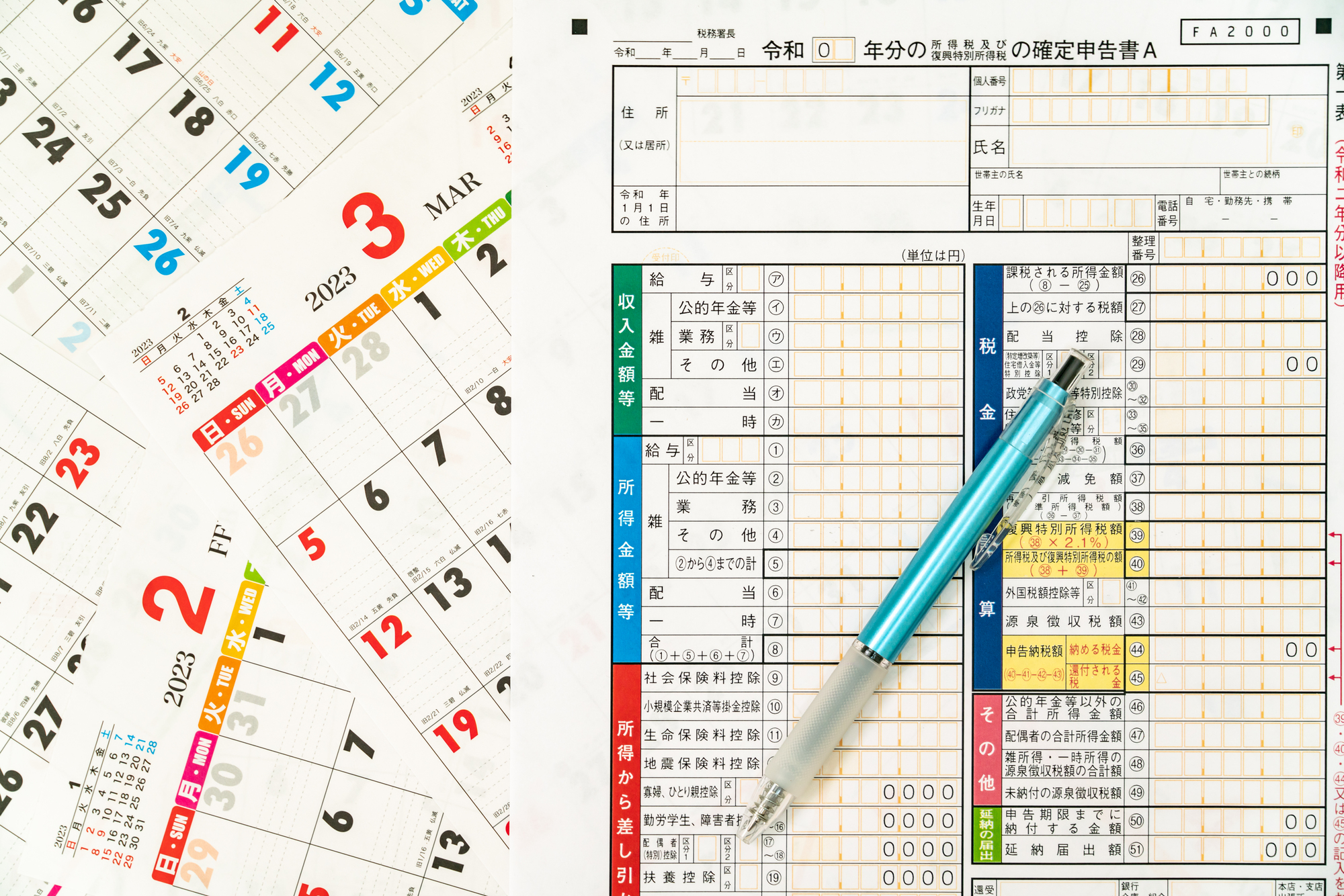
予定申告とは
この方法では、前事業年度の実績に基づいて納税額を算出するため、決算処理を行う必要がなく、仮決算に比べて手続きが簡単です。
算出方法
● 「法人税の予定申告額 = 事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日までに確定した前事業年度の法人税額 ÷ 前事業年度の月数 × 中間期間の月数(100円未満切り捨て)」
前事業年度で確定した年間の法人税額をもとに中間申告額を算出しますが、計算過程で生じた1円未満の端数は切り捨てし、計算結果の100円未満の端数も切り捨てます。
例えば、計算結果が174,999円だった場合、100円未満を切り捨てて174,900円が予定納税の金額です。
計算の注意点
6は1年の半分のため、つい前事業年度の法人税額の2分の1と計算してしまいがちですが、そうすると計算結果に微妙なずれが生じてしまいます。
例えば、前事業年度の法人税額が200万円の場合、100円未満を切り捨てた中間納付額は99万9,900円になります。
一方、200万円の2分の1は100万円となり、正しい計算をした場合と微妙に計算結果が変わってしまうため注意しましょう。
仮決算による方法
仮決算による方法とは
仮決算による方法では期末の申告と同様に決算処理を行うため、手間がかかる点に気を付けてください。
なお、仮決算に基づく納税額が予定申告の税額を超える場合、仮決算による申告を選択することはできません。
仮決算による、中間申告書には貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、勘定科目内訳明細書などを添付して提出する必要があります。
仮決算によるメリット
ただし、仮決算ではいったん決算時の手続きを行い、添付書類の作成を行う必要があるため、予定申告よりも手続きや計算の手間が増えます。
仮決算による負担と中間申告で減らせる納付額を比較して、仮決算による申告納付を行うか判断しましょう。
算出方法
6カ月が経過した時点で、棚卸資産の計上や未収・未払金の整理、減価償却などを含む通常の決算処理を実施し、中間決算書を作成します。
この中間決算書に基づいて法人税額を計算し、その金額を中間税額として申告・納付します。
中間申告書を提出期限までに提出しない場合
申告期限を過ぎてから仮決算による方法へ変更することはできないため、仮決算で中間申告を行いたい場合は、必ず期限内に書類を提出するようにしましょう。
法人税の中間納付をしなかった場合などの注意点
また、中間納付額を間違えて計算してしまった場合についても、併せて紹介していきます。
追徴課税
この期限を過ぎた場合、延滞税がかかります。
延滞税とは、税金が納付期限までに納付されない場合に、納期限の翌日から納付を行った日までで数えた日にちに応じて課される金額です。
まとめ

中間申告には前年度実績を基準とする中間申告(予定申告)と仮決算による中間申告があり、中間申告書を提出しなかった場合は、予定申告があったものとみなされます。
仮決算による方法は6カ月が経過した末日で決算を行い、その所得金額をもとに算出した税額を申告・納付する方法です。
例えば、3月決算の場合は9月末までの期間で決算を行います。
仮決算では期末と同様に決算処理を行うため手間がかかりますが、前事業年度よりも経営が悪化している場合は、中間税_額が少なくなります。
仮決算による方法を検討するとよいでしょう。
法人税の中間納付についてさらに理解を深めたい場合は、税理士に相談するのがおすすめです。
監修者情報

税理士法人スマッシュ経営
杉田 透(すぎた とおる)
資格:税理士
経歴
- 1959年
- 愛知県豊田市生まれ
- 1980年
- 名古屋国税局採用
- 2010年
- 法人税担当統括官
- 2020年
- 名古屋国税局退職
税理士登録
税理士法人スマッシュ経営 知立本社入社
所属税理士となる